2023年10月1日時点での総務省の人口推計によると、国内総人口1億2435万人のうち、昭和20年8月15日の終戦時に主に20代以上だった明治、大正生まれの人は35万8千人(0.3%)。戦後生まれは1億932万人(87.9%)。戦争体験者による口頭での記憶の継承は、年を追うごとに困難さを増している。「戦争が遠い歴史になってしまっている」と風化を懸念する声を聞き、改めて大学時代に受けた授業のことを話したい。
授業の一環で、吉田満著「戦艦大和ノ最期」の未発表テキストを読み合わせたことがあった。大日本帝国海軍が建造した大和型戦艦の1番艦である大和に乗り合わせた組員たちの決死の戦いを記録した、今となっては貴重な文献である。
生徒全員での朗読が終わった後、教授は涙ぐんで私達から顔をそむけた。
「ここに書かれている乗組員たちを思うと、私は涙が止まらなくなる」
教授の言葉と同じように、私は今までに感じた事のない深い悲しみと、水面に身を打ち付けたような胸の痛みを覚えた。戦争に関しての自分の無知さに恥じ入ると同時に、作者を始めとした戦艦の乗組員たち一人一人に鎮魂の思いを捧げ、その胸中と共鳴しようとすればするほど、項垂れた頭から涙が幾度も零れた。
授業の後、私はいてもたってもいられず、教授のもとに駆け寄った。
「先生、良かったです。今日の授業。今まで私が受けてきた授業で一番、心に残りました。ありがとうございました」
教授は、泣きはらした目もそのままに、私を見て深く頷いてくれた。あの時の先生の、子どものように赤らんだお顔と涙が、今になっても忘れられない。
本作は、体裁としては戦闘記録だが、すべてを一日で書き上げたとされる文語体の文章からは、単なる記録としてではない、人間の内から叫ばれる悲痛な思いや腹の底からの叫びの魂が、一語一語に乗せられている。読了した文庫版「戦艦大和ノ最期」から感じたのは、主に出撃までの乗組員たちの人間としての「生き様」だった。初出稿では、殆ど省かれている部分だ。彼等に、一人たりとも人間でない者はいなかった。ひとりの人間として、母より産まれ落ちた身体として、戦友や家族と過ごしてきた人間として、特攻艦に乗り、誰よりも近い場所にある死を見据えていた。だからこそ、その言葉、胸中には堪えがたきものがあり、逼迫されるほどに心を動かされるものがあった。
出撃前夜、最期の杯として無礼講で酒を飲み交わす晩。三千もの人間がみな一心同体の戦友として、志を同じとし、等しく覚悟を重ね、ひとところにいる事を想像させられるくだりだ。作者が廊下で二等水兵とすれ違った時の一文が以下である。
> 我らの墓場、互いに遠からず むしろ我と君とは、一つの骸なり
肩を抱えて、「お前」と呼びかけたき衝動湧くも、辛うじてこらう
この発せられなかった「お前」という声がもし発せられていたら、一体どのような抑揚で、どんな風に声帯をふるわせたのだろうと考えては、胸が締めつけられるような思いがした。共に死に行く者としての呼びかけの声は、毅然としているものなのだろうか、それとも、僅かな憐憫が含まれるのだろうか。否、その憐憫をも拭い去り、すべてを受け入れた声色なのだろうと、さまざまな思いを、このたった一文の合間に巡らせた。
最期を共にする戦友との決意もあれば、寄り添い過ごしてきた者との決別もある。作者が月夜、戦艦のハッチに降りた時に会話を交わした森少尉の言葉もまた、私には重々しく、そして忘れられない言葉となっている。
> 俺は死ぬからいい 死ぬ者は仕合せだ 俺はいい だがあ奴はどうするのか あ奴はどうしたら仕合せになってくれるのか
彼は自分が死ねることを幸せだと云う。そして、残された既婚者が自分とは違う人間と結婚して、幸せになることを願っているが、それを見届けられない。だから祈るしかない、叫ぶしかない。これが死にに行こうとする人間の魂の叫びだ、と感じ入った。これこそが魂からの叫びだ。祖国の名誉を背負った命を遂行する人間としての、並々ならぬ精神なのだ、と思った。現代の人間には、到底考えつかず、また真似の出来ない考えだ。それでもって、現代人である私には同じ考えを持つ術がない。なぜなら「義務である死に直面する」事が無いからだ。表立った戦争史には描かれない、生身の人間の叫びをここに見た気がした。「死」は正当、「死」は誉れ高い、「死ねる事」は最上の喜び。だがその「死ぬ」人間には、過去があった。過去に愛する人も、共にいた人もいた。その人に届けたかった思いも、ただ月夜の下で一人、静かに苦しみ、叫ぶしか無かった。言葉にならない、作者と同じ思いを強く感じた。
乗組員たちは人間であった。だから、生きている人間として当然の疑問を持っていた。
> 国のために死んで何になるのだ
彼らは自分が思うよりはるかに「人間」だった。人間として、もっとも考えるべき事を考えていた。この出撃前の場面は、未発表のテキスト全文には載っていなかった部分である。このような、祖国の報いに反するような考えを持っていた事は事実でありながら当初、それを記すことは許されなかった。
「死ぬことに価値をつけたい」。人間には平等に尊厳がある。しかし戦争というものはそれを無慈悲に奪い取る。それに投じられた人間は、口を噤んでただひたすらに、無謀に、死にに行くしかなかったのだろうと思っていたし、現実に起こったことはそれで間違いなかった。だが、彼等は確かに「死ぬとは何か」を考えていたのだ。死ぬことに意味が無い人間は居ない。産まれ落ち、母親から意味を付加させられるように。死んでしまえばその魂が昇っていき、灯が吹き消される。戦艦が沈没したら、何千もの命の大火が沈む。そのことについて、灯の一つ一つはこうして向き合っていたのだ。
> 進歩のない者は決して勝たない 負けて目覚めることが最上の道だ
乗組員たちの間で交わされる必敗議論の中、臼淵大尉は低く囁くようにしてこの言葉を言った。
新しく生まれてくるもののために死に、負けることで目覚め、道をつくっていく。自分たちはその踏み台になり、土壌になり、尤も直接に言えば犠牲になる。この言葉は、敗れることを避けられないであろう状況の中での真の答えであり、何のために死ぬのか、という問いの答えにもなりえるものだと私は感じた。この言葉こそが、終わりの見えない「死の価値」の問いへの、この時代、この戦争をしていた過酷極まりない瞬間の答えだったのだ、と。
負けることを最上として彼らは散った。負けることは分かっていた、自分たちが生きて帰ってこれないことも知っていた。だからこそ、この戦艦に乗っている間、どんな人間よりも「人間」であり、言葉を交わし、思いを叫び、熾烈極まりない死屍累々の戦場の中で、沈黙のままに散っていった。文庫版には、そんな乗組員一人一人の人間としてのドラマが描かれていたように思う。その言葉を、叫びを、私たちは忘れてはならない。この記録を読む前に、死んでしまってはならない。ここに書かれている人間の「生き様」を、何度も繰り返し刮目しなければいけない。
特攻隊員は、家族に別れを告げる時、「行って来ます」ではなく「行って参ります」と言う。帰って来る、という意味合いを避けるためだ。命、とは。生きて死ぬ、とは。重い考えだからといって、決して放棄してはいけない。本作こそ、現代人が読むべき、今は過ぎし時代の偉大なる遺産である。
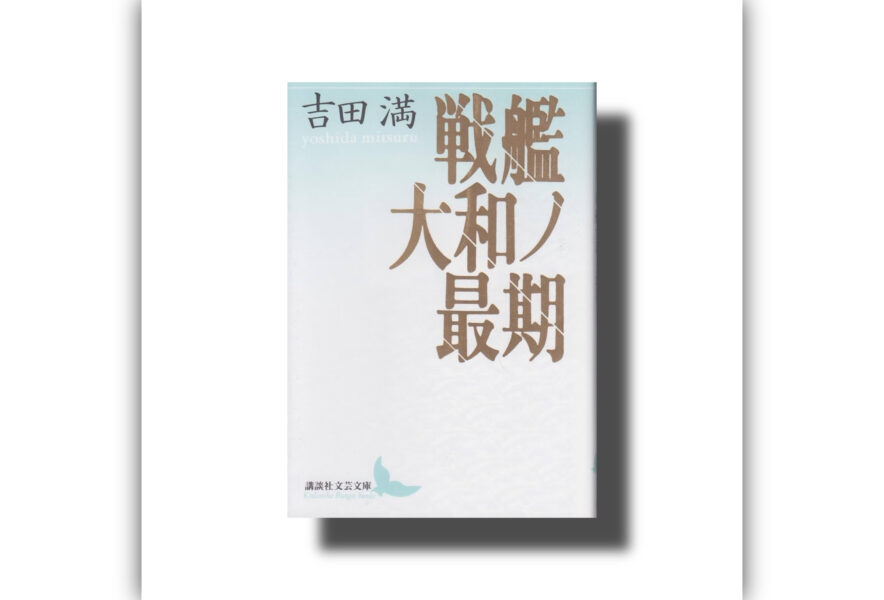
コメント